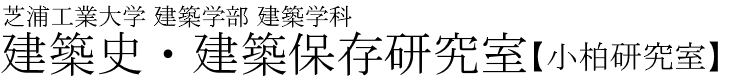見学 小柏研究室
2025/10/08
富貴寺(大分県豊後高田市・国宝/国指定史跡)見学
文責:川名美月(学部4年)
■富貴寺大堂(国宝)
建立:12世紀後半
構造形式:阿弥陀堂形式(一間四面堂)和様 正面三間 側面四間 宝形造 行基葺
富貴寺は平安時代に宇佐神宮大宮司の氏寺として開かれた由緒ある寺院である。
中でも富貴寺大堂は、宇治平等院鳳凰堂、平泉中尊寺金色堂と並ぶ日本三阿弥陀堂のひとつに数えられ、現存する九州最古の木造建築物であり、国宝指定となっている。本尊の阿弥陀如来像は970丈にも及ぶ一本の榧(カヤ)の巨木から六郷満山寺院を開基したとされる仁聞菩薩の手によって造られたと伝えられている。榧の木質は、油分が豊富でやや重厚、適度な堅さと弾力性があり、特有の芳香がある高級な材である。光沢のある淡黄色の色あいで、木肌はきめが細かく、緻密で美しい木目があらわれる。そのような材を970丈、つまり約2910mに値する長さのものを用いていることから格式の高さをうかがえる。
また、屋根は現存が少ないとされる行基葺を用いられている。平瓦の上に被せる丸瓦の上部が細く造られ、次の丸瓦が被るようになっている形状の瓦を使用して葺かれた工法を言う。通常の本葺きにおける丸瓦とは頭と裾の幅が逆さになったような形になっている。
■富貴寺本堂
建立:寛文6年(1666年)
構造形式:入母屋造 桟瓦葺(修理前)
富貴寺本堂は、国史跡「富貴寺境内」を構成する重要な要素の1つである。現在の本堂は平成30年度から全解体による保存修理が行われている。
この保存修理は建立以来(約300年経過)の初めての大規模な修理で、これまで部材の分解、木部の補修、基礎工事などが終わり、現在は柱や梁、屋根の叉首など建立当初の姿に復元、整備する組み立て作業が進められている。
■所見
富貴寺の大堂は、平安時代後期の阿弥陀堂形式をよく伝えている建物である。内陣は四本の柱で区切られ、その周囲を外陣とする構成となっており、阿弥陀堂らしい空間の特徴が見られる。しかし、内陣と外陣の柱筋が合っていない点は単純な阿弥陀堂とは異なっており、密教的な要素が取り込まれた可能性が考えられる。実際に、内陣を巡って念仏を唱えるという信仰のあり方が取り入れられた結果、奥まった空間が形成されたのではないかと推測できる。
構造面では、貫をほとんど使わず、太い柱を用いていることが特徴的である。特に柱の面を大きく取っている点は古い建築の特徴であり、江戸時代以降の建物と比較すると三倍ほどの太さがあるとされる。天井のつくりにも違いがあり、内陣は小組の格天井、外陣は折り上げ小組格天井とすることで、内と外の性格の違いを建築的に表現していることが分かる。
■参考文献
[1]豊後高田市,富貴寺,豊後高田市公式観光サイト,2024年5月10日
https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/1251.html (閲覧日:2025年9月3日)
[2]国指定史跡富貴寺境内保存管理計画書,豊後高田市教育委員会,2016年3月
https://www.city.bungotakada.oita.jp/uploaded/attachment/4433.pdf
[3] 文化庁,”富貴寺大堂”,文化遺産オンライン
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/124404,(閲覧日:2025年9月4日)