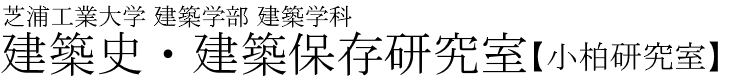見学 小柏研究室
2024/09/05
西園寺公望別邸「坐漁荘」(静岡県静岡市清水区興津地区)見学
文責:修士1年 胡 鐘毓
所在地:静岡県静岡市清水区興津地区(平成16年の復元建築)
概要
西園寺公望別邸「坐漁荘」は、日本の最後の元老として名高い西園寺公望により、大正9年(1920年)5月9日に静岡県興津に建てられた別荘建築である。昭和4年(1929年)に増築され、昭和46年(1971年)に主屋、付属屋、門、塀からなる一群が博物館明治村に移築され、重要文化財として展示公開されている。今回の見学先は、平成16年(2004年)興津地区に復元された西園寺公望別邸「坐漁荘」である。本稿の「所見」部分で述べられている内容は、この復元建築に関するものである。
坐漁荘は、数寄屋造りの近代和風建築であり、意匠や材料面だけでなく、要人の邸宅としての建築技法も取り入れられている。また、施主である西園寺公望の個人趣味や嗜好が随所に見られる建築でもある。
坐漁荘は、昭和4年(1929年)に応接室などの洋間や湯殿周りが増改築されたことが知られている。創建当初から敷地の変遷や空間機能の要求に応じて、現在の姿に至っている。
所見
主屋
木造平屋建一部二階建、屋根は入母屋造、桟瓦葺で軒先を銅板葺一文字葺とする。外壁は檜皮張で、一階も二階も数寄屋造である。玄関から部屋に入ると、欄間と竿縁天井が全体的に低く、長押がないことが確認された。また、施主である西園寺公望の文人趣味と思想を反映するため、かなり特殊な欄間形式が見られた。
一階の暖炉付き応接室や化粧室、浴室などは昭和初期に増築されたもので、設備面では、応接室の電気暖炉や化粧室の水洗トイレが当時の流行を取り入れている。一階洋室に接続する廊下の鴨居には太い丸太材が使用されており、数寄屋造の意匠がよく表現されている。また、洋間内の壁は漆喰塗りの大壁で、天井はちょうながけの化粧梁が表され、床は寄木張り、造り付けの棚が設けられており、これらの意匠が洋間としての特徴を示している。二階の廊下と階段の接続部分には鶯張りの工法が使用され、独特の意匠が造営されている。
付属屋
木造平屋建、寄棟造、屋根は桟瓦葺である。桁行三間半、梁間二間の建物であり、小壁は漆喰塗りの真壁で、軒は出桁造となっている。
参考文献
[1] 明治村著作・編集『西園寺公望別邸「坐漁荘」修理工事報告書』博物館明治村.2015