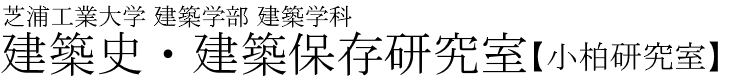見学 小柏研究室
2025/11/08
海住山寺(京都府木津川市・国宝)見学
文責:新村恵太(修士2年)
海住山寺五重塔(国宝)
建立:鎌倉前期 建保2年(1214)
構造形式:三間五重塔婆、本瓦葺、初重裳階付、銅板葺
鎌倉時代の五重塔としては現存唯一の例である。総高さは17.7mで、室生寺五重塔に次いで2番目に小さい五重塔である。心柱を初層天井上で止めており、また、初層に裳階がついているのも、現存の五重塔では類例が少ない。
今回は五重塔初層の御開帳の時期だったため、内部の拝観をすることができた。内部は四天柱に囲まれた方一間を内陣とし、四面に板扉を付けて厨子のような形態となっている。初層の天井は外陣・内陣ともに内法長押の上に折上小組格天井を張り、内陣は外陣よりも長押の位置が高いため天井がより高くなっている。
他の五重塔では組物を三手先にすることが多い中で、尾垂木付きの二手先の組物を用いており、全体の規模感に合わせた軒の出を抑えるための工夫を施していた。
裳階部分は、大面取りの角柱で、側柱と裳階柱を内法長押の高さに繋虹梁を架ける。裳階柱上は舟肘木で丸桁を受け、垂木を架ける。柱、舟肘木、丸桁、繋虹梁、垂木はすべて角材に大面取りを施しており丁寧な作りこみがされている。裳腰部の屋根勾配の緩やかさからも、平安時代からの過渡的な建築であることがわかる。
海住山寺文殊堂(国指定重要文化財)
建立:鎌倉後期
構造形式:桁行三間、梁間二間、一重、寄棟造、銅板葺
小規模な建物で、内部には柱を設けず、側柱に虹梁を架け、板蟇股と三斗組を載せて化粧棟木を受ける。組物は平三斗で、枠肘木の一方は巻斗を載せて虹梁を受け、一方は肘木尻を外に出す。中備の蟇股は、鎌倉時代らしい線が細く繊細な意匠だった。
参考文献
京都府教育委員会『国宝海住山寺五重塔修理工事報告書』(京都府教育庁文化財保護課,1963)
京都府教育委員会『重要文化財海住山寺文殊堂修理工事報告書』(京都府教育委員会,1964)