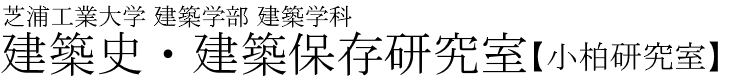見学 小柏研究室
2025/09/18
宇佐神宮(大分県宇佐市・国宝/重要文化財)見学
文責:赤塚美希音(学部4年)
◾️宇佐神宮本殿
所在地:大分県宇佐市南宇佐2859
創建:神亀2年(725)
建立:江戸時代末期、安政2年(1855)‐文久元年(1861)
区分:重要文化財(明治40年(1907)5月27日)
国宝(昭和27年(1952)11月22日)
構造形式:本殿は第一殿より第三殿に至る三棟より成る
内院 桁行三間、梁間二間、一重、切妻造、檜皮葺
外院 桁行三間、梁間一間、一重、向拝一間(但し第二殿なし)、檜皮葺、
造り合を含む
宇佐神宮は、延喜の制で名神大社に列せられた古い神社で、広幡八幡、宇佐神宮、八幡宇佐宮とも呼ばれ、神仏分離以前は、宇佐八幡宮弥勒寺(うさはちまんぐうみろくじ)と称していた。
全国に約11万の神社があるうち八幡宮が最も多く、全国に約46,000の社がある。宇佐神宮はそれらの総本社であり、日本三大八幡宮(宇佐神宮、石清水八幡宮、鶴岡八幡宮)のひとつである。
本殿には、八幡様として知られる応神天皇(誉田別尊)を主祭神として第一殿に祀り、続いて第二殿に比売神と第三殿に神功皇后(大帯姫神)を祀る三社殿から成り、東西に並んでいる。
小山田家(宇佐神宮の大々工職)の文書によれば、安政2年より文久元年に亘り式年造営が行われたことが知られ、これらの現存建物はその時のものであると考えられる。
三社殿ともに、切妻平入の正面三間、奥行二間の神明造の内院の前に、同じく切妻平入の桁行三間、梁間一間の外院を建て、これらを相の間で連結し、屋根の中央の谷に大きな雨樋を設けた典型的な八幡造を残している。
現在の建物は近世の造営であるが、その平面、立面は特殊な性質をもち、古式によるものと思われ、神社建築史上貴重な標本であるとして、京都の石清水八幡宮と並び、国宝に指定されている。
境内には、本殿の他に、北辰神社(県指定)やそれらを取り囲む回廊と南中楼門(県指定)、若宮神社(国指定)や神橋、呉橋(県指定)、能楽殿、宝物殿などが立ち並ぶ。その他、国の天然記念物に指定された社叢や弥勒寺跡がある。
宇佐神宮には、1300年という歴史を体感できる建造物、遺跡、自然が一体的に残され、八幡大神への信仰や神仏習合の歴史を考える上で極めて重要であるとして、境内全体と御許山はどちらも昭和61年(1986)に国の史跡に指定された。
本殿構造形式
平面:内部は内院を内陣とし、造り合と外院を外陣とする。その前面の一間を向拝(第二殿はなし)とし、内・外陣の四周に切目縁を廻すが、内外陣境筋で段違いとする。
軸部:身舎柱礎石間の受石上に地覆を置く。
身舎円柱、向拝唐戸面取角柱で桁行、梁行とも足固貫、内法貫を通し、内院と外院は繋梁でつなぐ。内・外院周囲に切目長押、内法長押を廻すが、いずれも内・外陣境筋で脊違をする。柱上には内・外院、向拝とも舟肘木を組み、軒桁を受ける。
塗装:内・外院とも外部は弁柄朱漆塗を主とし、腰壁、蔀戸綿板を胡粉塗、地覆、蔀戸、四分一、懸魚、破風眉を黒漆塗とし、高欄、建具、長押、垂木、懸魚、破風の各所に鍍金または漆箔押の飾金具を打つ。
◾️南楼門
構造形式:三間一戸楼門、入母屋造、檜皮葺
建立:寛保2年(1742)、明治期修理
区分:県指定文化財(昭和43年3月29日)
南中楼門は本殿を取り囲んで南回廊のほぼ中央に立つ。花崗岩基壇上に南面し、梁行中央柱通りに回廊外側の柱筋が一致し、下層の後一間は回廊より一段低く床板を張る。前方中央一間の床は花崗岩敷き、左右の間は一段高く床を張り随身像を祀る。円柱は上部付きで、地・腰・内法長押と頭貫、台輪で固める。組物は拳鼻付き三手先斗で,三手先目で上層の縁桁を支える。中央間に外開き吹寄せ格子戸をたて、両脇間正面、内側、背面は腰高連子窓、側面横板落し込みとする他、回廊に接続するので、吹放しである。天井は格天井である。上層は円柱に切目・内法長押、頭貫、台輪を廻す。組物は和様尾垂木付きの三手先斗である。中備は、中央間の詰組で、他はない。軒は二軒。扇垂木で、周囲に軒支輪三段を付ける。妻飾は虹梁大瓶束である。正面中央間に外開き格子戸をたてる以外、横板落し込みで、この手法も珍しい。全体的に朱を中心に塗るが、垂木の木口などは黄色。頭貫などの絵様は黒色や白色を用いる。扉などに金色の飾り金物を豊富に使用する。
◾️八幡造
奈良時代に入ると、仏教とともに伝来した仏寺建築の影響を受けた神社の形式が現れる。すなわち、仏寺のように反りの付いた屋根となり、土台を設けて縁側と手摺を設け、さらに仏像を真似て神像と呼ばれる礼拝仏を祀るようになった。
平安時代に入ると、神社に増して信者を集めるようになった寺院に対抗するために、神は仏が姿を変えたものであるという「本地垂迹説」を唱え、参拝者を集めようとした。そのため、神社はいっそう仏寺色を強め、本殿だけではなく回廊や楼門、あるいは塔が設けられるようになる。このような仏寺の影響を強く受けた形式の代表例の1つが八幡造である。
八幡造は、仏寺の双堂の様式を取り入れたと言われ、本殿と奉祀のための前殿の二頭が前後に「相の間」と呼ばれる部屋で継がれた形式で、その後、人を神として祀るための様式である権現造として発展することとなる。
八幡宮は全国に多くあるが、現存する木造八幡造の神社は10社に満たず、更にその中で本殿として木造八幡造を残しているのは、大分県の宇佐神宮本殿(国宝)、柞原八幡宮本殿(重文)、京都府の石清水八幡宮本殿(国宝)、愛媛県の伊佐爾波神社本殿(国宝)の4つのみである。
◾️所見
参道は緩やかな坂になっており、道中若宮神社をはじめとする多くの摂末社が点在していた。それだけ境内も広大であり、宇佐神宮の荘厳さが感じられた。参道は豊かな自然に囲まれており、社殿の朱が緑の中に際立つ景観を形成しており、大きな鳥居や楼門を潜る度に浄化される気持であったが、その先に辿り着いた南中楼門と本殿は、その規模と意匠の美しさにおいて特に印象的であった。
上宮へ至るまでの参道とは対照的に、自然の開けた空間にある勅使門は、花崗岩の基壇の上に三手先組物で縁と屋根を支えた楼門形式となっている。これにより構造的な迫力と安定感を感じることができた。南中楼門は同年度に屋根の葺き替えや塗装の修復こともあり、非常に色彩が鮮やかであった。日光を受けて白く反射した花崗岩と朱の対比が美しく、一際華やかであった。
本殿についても、2015年に実施された修理工事により屋根の葺き替えや塗装の塗り直しが行われたが、それから10年経った現在でも非常に保存状態が良かった。
本殿には南中楼門とは異なり三手先組物のような複雑な組物はなく、簡素な舟肘木による組物が採用されている。また蔀戸などの存在からも、平安時代の宮殿建築の雰囲気が感じられた。一見簡素な様式を持つ一方で、漆喰の白や漆の黒、朱の彩色や錺金具の金など、鮮やかな色彩が施されており、全体として華やかさと格式を兼ね備えていた。
宇佐神宮は建築的にも歴史的にも高い価値を有しており、その保存状態や参拝客の多さからも、現在に至るまで広く人々に親しまれていることがうかがえた。
参考文献
[1] 財団法人文化財建造物保存技術協会『国宝 宇佐神宮本殿修理工事報告書』(宇佐神宮,1985)
[2] 大分県教育委員会, 宮崎県教育委員会, 鹿児島県教育委員会, 沖縄県教育委員会『九州地方の近世社寺建築 〈2〉』(東洋書林,2003)
[3] 文化庁「宇佐神宮本殿」(『文化遺産オンライン』, https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/110754,2025/8/29)
[4] 宇佐神宮庁「八幡総本宮 宇佐神宮」( http://www.usajinguu.com/,2025/8/29)
[5] 宇佐市観光戦略会議「宇佐神宮御鎮座1300年記念」( https://www.millennium-roman.jp/usajingu1300/,2025/8/29)