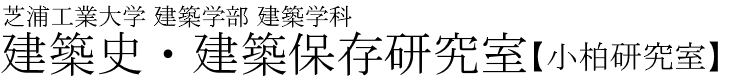見学 小柏研究室
2024/10/08
Toro Ruins (Shizuoka City, Shizuoka Prefecture, Special Historic Site) Tour Report
文責:伊東和真(学部4年)
概要
安部川と藁科川がつくった扇状地である静岡平野、洪水により形成された自然堤防上に多くの集落が造られた。弥生時代後期にあたる1世紀ごろの集落と推定される。発掘されたのは戦時中の昭和18年(1943)、軍需工場建設の際である。戦後昭和22年(1947)には日本で初めての総合的な発掘調査が行われ、大量の土器・木製品など出土品とともに8万平米を超える水田跡、住宅遺構が検出された。この発掘調査をきっかけに日本考古学協会が発足されるなど、日本の考古学のターニングポイントと言っても過言ではない。
所見
住居(復元)は外周に溝を掘り、土を盛った周堤を羽目板と杭で護岸され、床面は外部の地表面と同じ高さである。竪穴状平地建物と呼称され、一般に知られる竪穴住居とは一見似ているものの異なる形式である。低湿地の集落であったことから雨水の侵入防止であったと考えられる。床を掘り下げなかったのは地下水位の高さからであると言われる。
上屋は四本の柱と梁桁に、登り梁と棟木・母屋で茅葺屋根を支えるつくりとなっているが、再現された建材の加工が同時代の技術・道具で可能なものだったかは疑問である。
高床建物は倉庫と別に祭殿が一棟発見されている。八本の掘立柱で形は倉庫と同じだが、妻面左右に棟持柱という特徴的な柱を持ち、規模も集落内で最も大きい。
参考文献
静岡市立登呂博物館 https://www.shizuoka-toromuseum.jp/ (2024年10月8日閲覧)