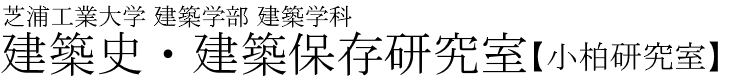見学 小柏研究室
2025/09/02
石山寺本堂(滋賀県大津市・国宝) )見学
文責:藏重直輝(学部4年)
概要
建立:永長元年、慶長7年(礼堂)
構造形式:本堂 桁行7間 梁間四間、相の間 桁行一間 梁間七間、礼堂 懸造 桁行九間 梁間四間、本堂及び礼堂 寄棟造、両党を相の間の屋根でつなぎ礼堂の棟をこえて破風をつくる、総檜皮葺
所在:滋賀県大津市石山寺
石山寺の本堂は、もともとあった本堂に対し、崖の方向へ「相の間」を挟んで「礼堂」を増築したことで、現在のような懸造の姿となった。
屋根の構造は、本堂と礼堂が共に寄棟造であり、その間をつなぐ相の間の屋根が礼堂の正面まで伸びて、印象的な千鳥破風を形作っている。
建物は懸造のため、参拝者は礼堂の側面から出入りする。内部は、本堂、相の間、礼堂が間仕切りや床、天井の仕上げによってそれぞれの空間として明確に区切られている。しかし、物理的には分かれていても、礼堂から本堂のご本尊まで伸びる「結縁の綱」によって、参拝者と仏様の精神的なつながりが保たれる工夫がなされている。また、礼堂の内部は、虹梁や貫といった部材を多用した造りのため、柱の数が多くなっている。
所見
石山寺の本堂は、もともとあった本堂に、参拝スペースである礼堂とそれらをつなぐ相の間を増築して現在の姿になっている。そのため、本堂内部の正面を見ると、増築に伴う屋根や空間の変化によって、かつての軒先にあたる垂木などが現しになっており、以前の姿を示す多くの痕跡が確認できる。
外観に目を向けると本堂は組物が平三斗で、内部の虹梁の先端を鯖尻で収めている。一方、礼堂は出三斗を用い、大きく湾曲した繋虹梁によって向拝を形成する。さらに他の部分では舟肘木が多用されており、こうした外観の様式の違いは、建物が異なる時代に建てられたことの感じさせ、歴史の変遷を物語っている。
このほか、懸造ならではの足場の貫空間の活用や、柱と貫の楔止めの楔の形状、左右での組み合わせの違い細部にわたる工夫も見ることができた。
参考文献
・国指定文化財等データベース https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/1315 (閲覧日9月1日)
・滋賀縣教育委員會事務局社會教育課『國寳石山寺本堂修理工事報告書』