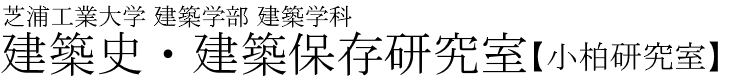見学 小柏研究室
2025/09/03
Visit Saikyo-ji Temple (Otsu City, Shiga Prefecture, a nationally designated important cultural property)
文責:新村恵太(修士2年)
〇西教寺本堂
建立:江戸中期 元文4年(1739)
構造形式:桁行七間、梁間六間、一重、入母屋造、向拝三間、本瓦葺
正面2間を外陣、中央桁行3間、梁間4間を内陣、その左右2間を脇陣とする。
外陣は入側柱と内外陣境柱に虹梁を架けることで柱を抜き、正面側を化粧屋根裏、内陣側を鏡天井とする。虹梁には大瓶束を載せ、その上に大斗、枠肘木を2段載せて出組とし天井桁を受け、天井桁の一段下の巻斗は、入側柱上の出組から伸びる海老虹梁を受ける。内外陣境は、内陣の隅柱を桁行方向の虹梁を架けることで、柱に遮られることなく内陣を拝むことができる。
内陣は、中央寄りに四天柱を置き、柱の上部や頭貫、台輪に彩色を施す。天井は全体が高く小組格天井である。組物は尾垂木付きの二手先で、尾垂木には龍、拳鼻は獏の彫刻が施されていた。四天柱間は詰組だが、組物の間にさらに蟇股を入れる。
内陣、外陣、脇陣の各境は建て登せ柱となっており、外から柱の違いも見ることができた。内部では、その柱を中心に虹梁などを差しており、建物のコア部分を形成しているように思えた。
全体的に組物や細部意匠が作りこまれ荘厳な印象があり、また構造にも工夫が見られ、近世らしい仏堂だった。
○西教寺客殿
建立:桃山(1597)
構造形式:桁行27.1m、梁間15.3m、一重、南面入母屋造、北面切妻造、杮葺
本堂の西に東面して建つ。東西2列で東側には5つの座敷が並び、北から控間、鶴の間、猿候の間、賢人の間、花鳥の間である。花鳥の間の西は帝鑑の間(上座の間)で、西側に床と棚を設ける。客殿の5室には障壁画が描かれており荘厳な雰囲気となっていた。
東、南面に広縁と落縁を廻しているが、庭園のある広縁側に床を設けてるのが一般的だが、西教寺客殿の帝鑑の間は逆となっていた。
北西の1室は茶室であり、面皮付きの長押を用いるなど数寄屋風の意匠となっている。ここでは庭園が西側に設けられ、客室の庭園というよりも、茶室からの眺望を想定した庭園となっていた。
西教寺と同じ大津市内の代表的な客殿である光浄院客殿(建立1600年)勧学院客殿(建立1601年)と比較しても、上段の間の向いている方向や、庭園が裏側の機能としていることなど、数年の建立の差でも異なる点も多くあり大変興味深かった。
参考文献
文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/145068 (2025.9.1閲覧)
滋賀県教育委員会『近畿地方の近世社寺建築. 1(滋賀)』(東洋書林,2003)
大熊喜邦 監修『国宝書院図聚 第5』(洪洋社,1940)