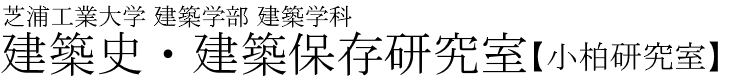見学 小柏研究室
2024/08/12
毛利氏庭園(山口県防府市・国指定名勝、国指定重要文化財)見学
文責:新村恵太(修士1年)
概要
戦国時代から江戸時代にかけての大名であった長州藩毛利家、毛利宗家が家憲に定めた常駐の地として計画されたもので、大正初期に建設された。84,000 ㎡の広大な敷地は、北側に本邸の建造物、南側に池泉などの庭園部分に分けられ、広大な池泉回遊式庭園である。敷地が毛利氏庭園として国指定名勝、建造物は旧毛利家本邸(本館、女中部屋、台所、洗濯所、奥土蔵、台所付倉庫、用達所倉庫、二階建物置、画像堂、石橋、門番所、本門の11棟)として国指定重要文化財に指定されている。
毛利氏庭園(国指定名勝)
敷地南側の庭園部にある池泉はひょうたん池と呼ばれており、池泉北に滝が配置され南へと池が広がっている。4mほどの高さの滝には、巨大な石を用い、周囲にも大きな石を用いる豪華さであった。また庭園の各所には、他所では見ない大きな燈籠や石組が配置されており、庭園南部に位置する建造物からも大きく目に入るサイズ感であった。
旧毛利家本邸本館(国指定重要文化財)
建立: 大正5年(1916) (棟札)
構造形式: 客間部2階建、他平屋建、入母屋造、桟瓦葺
平面: 南西に客間、南東に三棟の居間を並べ、中庭を挟んだ北西に詰所、北東に食堂を設ける。西側に玄関と車寄せを設け、玄関広間と2室の応接室が南北に並ぶ。
客間は、1階2階ともに東から、広間、次の間、三の間が並び、庭園に面する南側には一間の畳廊下と板縁を設ける。1階は、広間の東に床と棚、床の東側に付書院を設け、壁には砂子蒔で雲海を表現し、各座敷は筬欄間で区切っていた。広間の天井は折上小組格天井、次の間と三の間は小組格天井としており、各座敷の格式が明確に表現されていた。また1階は、内法長押と蟻壁長押を設けることで、天井下部の柱を隠して軽快な印象を持たすとともに、天井高をあげることで開放的な印象を受けた。
2階は、1階と同様に広間の東に床と棚、トコの東側に付書院を設けるが、付書院を3畳として、上段之間の扱いをしていた。壁は1階と異なって広間は漆喰壁、次の間、三之間は砂壁として、襖に砂子蒔の雲海が描かれ、各座敷は筬欄間で区切られている。天井の仕様についても、広間は格天井、次の間、三の間は竿縁天井としており、1階と同様に座敷の格式が表現されているが、1階よりも格式が低いことがわかる。1階の天井が高いことから、2階は通常よりも高い位置から庭園を眺望することができ、庭園外の市内や海まで臨むことができた。また、1階2階の客間は、柱間が桁行方向に2間半、梁間方向に3間飛ばしており、庭園の眺望を遮らない造りをしていた。
大名家の邸宅らしい、豪華絢爛な建築と庭園であり、格式の高い建築と、スケールの大きな庭園を見ることができ、とても興味深い場所であった。
参考文献
文化庁『月刊文化財579号』第一法規,2011年12月
重森三玲,重森完途『日本庭園史大系第30巻』社会思想社,1974