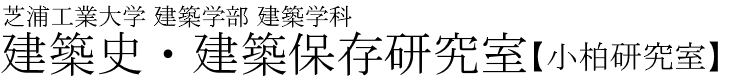見学 小柏研究室
2024/06/18
三徳山三佛寺(鳥取県東伯郡三朝町・国宝)見学
文責:長澤葵(学部4年)
概要
三徳山三佛寺は、標高899.9mの三徳山にある天台宗の古刹である。
三仏寺奥院(投入堂)
昭和27年10月16日国宝指定
創建:平安
構造:桁行一間(背面二間)、梁間二間、流造、両側面に庇屋根及び隅庇屋根付、檜皮葺
愛染堂
構造:桁行一間、梁間一間、単層切妻造、檜皮葺
外側柱=約182mm(面内=約121mm)、丸柱=約273mm
三徳山の岩窟の崖にかけられた小規模な建築で、通し柱と筋違のみで構成されており、日本最古懸造建築の遺構である。母屋の北と西側のみに庇を廻らし、東に愛染堂が付随しているため、左右非対称の建物となっている。愛染堂と投入堂の間に床が少し下がった部分があり、岩や柱にしがみつきながら登った後、修験僧はそこから投入堂に入るのだと考えられる。また、投入堂は太い柱を細く優美に見せる柱の大きな面取り、ゆるやかな曲線の檜皮葺の屋根、母屋の周りに庇を回らす平面構成や部材の年輪年代測定から平安時代に建立されたと考えられる。
三仏寺地蔵堂
昭和32年2月19日重要文化財指定
創建:室町後期
構造:桁行四間、梁間三間、単層入母屋造、背面軒唐破風付、こけら葺き
方三間に正面一間、堂の四方には縁
角柱=158mm(面内=140mm)、中央丸柱=227mm
現在の地蔵堂の建物は、内陣の舟形天井の化粧や絵模様の様式から室町時代後期に建てられたと推定される。平行に伸びた垂木が二重になっており、肘木が確認できる。
三仏寺文殊堂
昭和32年2月19日重要文化財指定
創建:室町後期
構造:地蔵堂同様
外周柱=164mm(面内=152mm)、それ以外柱=212mm(面内=167mm)
内部の扉の金具に「檀那南条備前守天正8年(1580)3月吉祥日」の銘がある事から文殊堂自体も室町時代後期(永禄年間:1500年代)に建てられたと推定される。床下架構部は柱貫に加え筋違が使われている。地蔵堂同様、平行に伸びた垂木が二重になっており、肘木が確認できる。
地蔵堂と文殊堂の二棟は規模様式が同じであるが、文殊堂の内陣天井が鏡天井であることや内陣中央2本の柱が円柱であること、柱天に梁が通し木口部分には雨蓋をつけていることから、造りが地蔵堂より整っており、地蔵堂の後に文殊堂が建てられたと考えられる。また修験僧は文殊堂の背面側に沿って崖を登ったとされることから、背面に破風をつけたと考える。
参考文献
三徳山三沸寺ホームページ https://mitokusan.jp/
文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/140667
文化財建造物保存技術協会編著 国宝三佛寺奥院(投入堂)ほか三棟保存修理工事報告書