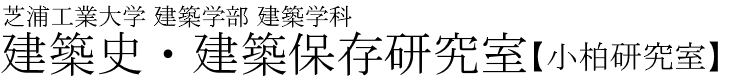見学 小柏研究室
2025/02/24
五台山竹林寺(高知県高知市・書院(国指定重要文化財)・庭園(国指定名勝))
文責:岩崎佑亮(修士1年)
・概要
本堂:国指定重要文化財 室町後期/1467-1572
木造、桁行五間、梁間五間、一重、入母屋造、向拝一間、こけら葺
書院:国指定重要文化財 江戸後期/1816
木造、桁行20.2m、梁間14.3m、一重、入母屋造、玄関附属、桁行12.8m、
梁間7.9m、切妻造、南面車寄付 向唐破風造、銅板葺
竹林寺庭園:史跡名勝天然記念物
竹林寺(ちくりんじ)は、高知県高知市五台山に位置する真言宗智山派の寺院であり、四国八十八箇所霊場の第三十一番札所として広く知られている。その創建は奈良時代の神亀元年(724年)に遡り、聖武天皇の勅願により高僧・行基が唐の五台山になぞらえて開創したと伝えられている。この地は文殊菩薩の霊場として「南海第一道場」と称され、多くの学僧や名僧が集う学問寺院としての歴史を有している。
・所見
本堂(文殊堂)
本尊である文殊菩薩を祀ることから「文殊堂」とも称される本堂は、寛永21年(1644年)に土佐藩二代藩主・山内忠義公によって造営された。現存する竹林寺最古の建造物であり、国の重要文化財に指定されている。建築様式は室町時代の特徴を持ち、一重入母屋造、五間四方、杮葺(こけらぶき)の屋根が荘厳な佇まいを見せている。特に、唐様の軽快な曲線を描く軒反りや、放射状に広がる扇垂木(おうぎだるき)など、密教寺院建築の中でも独特の意匠が随所に見られる。
書院
文化13年(1816年)に建築された書院は、六室を配した主体部の南面と西面に広縁を巡らせ、東面には玄関が設けられている。内部では、背面西側の上段の間に床、棚、付書院が配置され、背面中央の部屋では側方に床を設け、後方の庭園を望む座敷とするなど、独特の構成が特徴的である。四国地方における近世の書院建築として貴重であり、土佐地方特有の細部意匠を持つ上段の間や、庭園鑑賞を意図した開放的な裏座敷など、藩主祈願寺としての特質や地方的特色が見られた。
竹林寺庭園:竹林寺の庭園は、客殿・書院の周囲に広がり、大きく三つの区域で構成されている。いずれも江戸時代後期の池泉庭園の特徴を備え、地割や意匠に基づいて作庭されている。特に、客殿の西庭では、石段状の直線的な護岸が水面を軒先近くまで引き寄せ、狭い水面に広がりを持たせている。また、山裾の石組や傾斜面に配置された景石群は、繊細で洗練された雰囲気を醸し出している。
参考文献