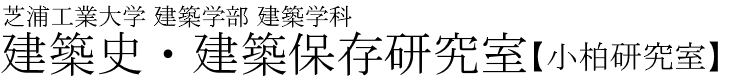見学 小柏研究室
2024/08/17
Visit Toko-ji Temple (Hagi City, Yamaguchi Prefecture, a nationally designated important cultural property)
文責:楊 暢(学部4年)
概要
黄檗宗護国山東光寺は、萩藩三代藩主毛利吉就により、萩出身の高僧慧極道明禅師を開山として、元禄四年(1691年)に創立された。最盛期には堂宇が30棟を超えていたが、明治の廃仏毀釈による伽藍縮小の結果、現在は近世の遺構として大雄宝殿・鐘楼・三門・総門・方丈の五棟が残されている。総門・鐘楼・大雄宝殿の三棟は元禄六年(1693年)から元禄十一年(1698)の間、三門は遅れて文化九年(1812年)に建立されたものである。これら四棟は昭和41年6月11日に重要文化財に指定された。現在の伽藍配置は西面して、総門・三門・大雄宝殿が中軸線上に並び、大雄宝殿の前方北寄りに鐘楼、後方南寄りに方丈が建っている。また、大雄宝殿の裏手は毛利家奇数代の墓所(国指定史跡)がある。
所見
・伽藍配置
中央軸に主な建物を配置し、その左右対称に他の建物が配置されるのは、黄檗宗寺院の伽藍の特徴である。東光寺が最盛期だった頃、その伽藍は黄檗宗が各地に広まった時期の中でも最も整ったものとされる。現在では多くの堂宇を失っているが、総門・三門を通り、大雄宝殿に至る際に中軸線が強調された配置が感じられた。
・総門
三間二戸八脚門。切妻造、本瓦葺で、中央棟を一段高く切り上げる。
この総門は、黄檗宗寺院特有の門の形式を示す遺構である。
・三門
三間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺、両山廊付。山廊は、各桁行二間、梁間二間、切妻造、本瓦葺。
この三門は唐様を基調としたが、屋根大棟の中央に宝珠瓦、両端に鯱瓦を据えるなど黄檗宗寺院の特色のある細部手法が見られる。
・大雄宝殿
桁行正面五間、背面三間、梁間四間。一重裳階付、正面一間通りは吹放ちとする。入母屋造、本瓦葺。
仏殿の前に月台を設け、石製の繰形付角礎盤の上に柱を立てることや、豪華な天井装飾などの手法から、黄檗宗寺院の壮大かつ荘厳な美しさを感じた。また、主屋と裳階の特異な形式を持つ組物には、山口の大工たちの創作や工夫が込められているだろう。
・鐘楼
桁行三間、梁間一間、一重裳階付、入母屋造、本瓦葺、裳階桟瓦葺。
鐘楼は明治期の境内建物縮小にあたって、接続していた回廊が撤去されたなど一階部分を大改造することが判明された。昭和六十三年~平成四年の解体修理では、間仕切りの撤去や階段の復旧などの現状変更が行われ、建立当初の姿に復旧された。この黄檗宗特有の裳階付きの鐘楼の形式は、文化財的価値が高いところだと思う。
参考文献
文化財建造物保存技術協会(1993)『重要文化財 東光寺鐘楼・三門・総門・大雄宝殿 保存修理工事報告書』
東光寺HP < https://www.toukouji.net/ > 2024年7月20日閲覧