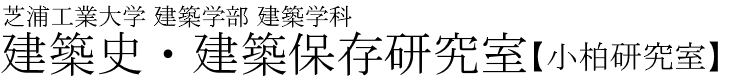見学 小柏研究室
2025/10/01
Visit Buzen Zenkoji Temple (Usa City, Oita Prefecture, a nationally designated important cultural property)
文責:金原秀太
構造形式:
桁行七間、梁間五間、一重、寄棟造妻入、向拝一間唐破風付、本瓦葺。軒は二軒角繁垂木、組物は出三斗、木鼻は禅宗様。内陣は折上格天井、外陣は大虹梁上に二重枠肘木を置いて化粧棟木・化粧垂木を支える
所在地:大分県宇佐市下時枝
建立年:室町時代中期(1393〜1466年頃)
区分 :本堂 重要文化財
歴史的背景
豊前善光寺は浄土宗の寺院で、宇佐市の芝原地区に位置する。創建は平安時代中期の天徳2年(958年)と伝えられ、念仏踊りで知られる空也上人が、信濃善光寺参籠ののち九州に下り、宇佐の地に寺を建立したと伝承されている。
本堂の建築的特徴
現存する本堂は、室町時代中期に再建されたもので、国の重要文化財に指定されている。
建築形式は桁行七間、梁間五間、一重、寄棟造妻入で、本瓦葺の屋根に唐破風を備えた向拝を持つ。向拝は元禄期の補修によるものである。構造的には、軒に二軒角繁垂木を配し、組物は出三斗とするなど和様の枠組みに禅宗様の意匠を折衷的に取り入れている点が特徴的である。木鼻の造形にも禅宗様が見られ、外来要素の導入が地方寺院建築にも反映されていることを示している。
内部構成は内陣と外陣に分かれ、内陣天井は折上格天井とする。一方の外陣は大虹梁を架け、その上に二重枠肘木を置き、化粧棟木と化粧垂木を支えることで、力強く実用性に徹した屋根裏空間を形成している。このように簡素で無骨な意匠ながら、建築全体に緊張感と迫力を与える構成は中世寺院建築の特色をよく示している。
巻斗の側面部に注目し、本堂の入り口上部のものと向拝部分のものを比較すると、向拝部分の巻斗の方が若干横長になっていることが確認できる。このことからも向拝は後から増築されたことがわかる。
所見
本堂は妻入り形式の屋根を有し、さらに後付けの向拝を備えている点や、和様と禅宗様が両方取り入れられている点など、独特な設計だと感じた。比較的広い境内には、鐘楼や閻魔堂などの建造物がゆとりをもって配置されており、特に本堂よりも規模の大きい庫裡が印象的であった。境内全体としては迫力を感じさせる一方で、広々とした空間によって落ち着いた雰囲気も醸し出されていた。
参考文献