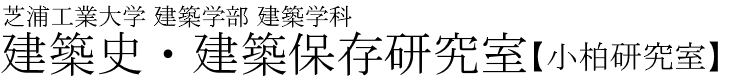見学 小柏研究室
2024/08/12
椎尾山薬王院(茨城県桜川市真壁町・県指定文化財)見学
文責:新村恵太(修士1年)
概要
標高200mの椎尾山中にあり、延歴元年(782)最仙上人が開山したと伝えられる古刹である。境内は本堂、三重塔、仁王門で構成。樹齢300年~500年のスダジイが群生し「椎尾山薬王院の樹叢」として県の天然記念物にも指定されている。
本堂(市指定文化財)
建立:延宝8年(1680)
構造形式:梁間五間、桁行五間、入母屋造、銅板葺、正面一間向拝唐破風付、四周に高欄付きの縁を廻す
大工桜井瀬兵衛によって建てられた。桁行三間、梁間二間の内陣と正面二間の外陣、背面と側面に一間の脇陣で構成される。外陣は虹梁大瓶束にして柱を抜くことで、二間分の柱がない礼拝空間を確保している。内陣と外陣の正面の境は、中敷居と格子戸で区切られており、密教系の仏堂の特徴を見ることができた。外陣外部の組物は尾垂木つきの三手先、内部を出組にして虹梁を受けており、これによって軒先を深く、天井を高くするための工夫であると考えた。
仁王門(市指定文化財)
建立:元禄元年(1688)
構造形式:三間一戸、入母屋造、銅板葺
本堂と同じく桜井瀬兵衛によって建てられた。三間一戸の楼門形式で、一層目には貫、二層目は長押で構造を固める。一層目の中備には彫刻を施した蟇股、二層目は間斗束だった。迫力ある仁王像が祀られていたが、今は別の場所で拝むことができる。
三重塔(県指定文化財)
建立:宝永元年(1704)
構造形式:方三間、宝形造、銅板葺
成田山新勝寺の三重塔と同じ、桜井瀬左エ門を大工棟梁として建てられた三重塔である。各層、中央間に板戸、脇間に板壁を設けており、初層の脇間にはパネル式の彫刻がはめられている。また、内法長押や台輪長押、垂木などに朱色の彩色が残されていた。尾垂木には龍の彫刻が彫られ、胴体は朱色で目の部分に金箔が貼られていることもわかった。枝数に関して、初層は脇間8枝、中央間12枝の計28枝、二層目は脇間8枝、中央間9枝の計25枝、三層目は脇間7枝、中央間8枝の計22枝で、中央間を大きく逓減させていることがわかる。
薬王院三重塔と新勝寺三重塔とは、板軒にして極彩色である点が相違であるといえるが、尾垂木に龍の彫刻を持っていることや、逓減が同様であり、類例の比較が今後も検討できると考えた。
今回、三重塔の内部も見学させていただいた。一層目の天井上から伸びている心柱は、上の相輪部分までどの部材にも接することなく立ち上がっており、今まで図面上でしか見てこなかったものを自分の目で見て構造を理解することが出来た。また、各組物の尾垂木も内部まで伸びており、構造的に重要な役割を持っていることを見ることができ、非常に学びの多い機会だった。
参考文献
桜川市観光協会 http://www.kankou-sakuragawa.jp/page/page000063.html(2024.7.14閲覧)
文化財建造物保存技術協会編『重要文化財新勝寺三重塔修理工事報告書』新勝寺, 1984