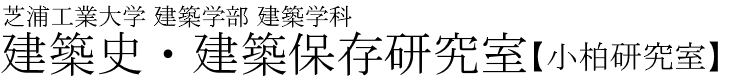見学 小柏研究室
2025/08/08
Visit Jorakuji Temple (Konan City, Shiga Prefecture, a national treasure)
文責:新村恵太(修士2年)
〇常楽寺本堂
建立:室町前期(1360)
構造形式:桁行七間、梁間六間、一重、入母屋造、檜皮葺、正面三間向拝付き
正面二間を外陣、中央桁行五間、梁間二間を内陣、背面二間を後陣で構成される。
外陣は、中央の四通りに側柱から内外陣境の柱に虹梁を架けることで、柱を抜く。また、虹梁に三斗組を載せて天井桁を受け、外陣全体が組入天井となっている。
内陣は、内外陣境柱から内陣背面の柱に梁を置き、束と花肘木を立てて柱を抜き、天井の格縁を受ける。天井は支輪で折り上げた格天井であるが、柱の上には組物を置かない簡素な作りだった。
後陣は入側柱が隅の1本のみ柱を抜いている。後陣入側柱と内陣背面柱を梁で繋ぎ、柱筋に桁を架け、その上に側柱上の丸桁まで繋梁を入れ、その上に斗を載せ、側桁を受ける。天井は、繋梁上に入側柱筋から背面にずらした位置に束を置いて天井桁を受け太い竿状の天井、入側柱と内陣背面柱の間は垂木状の天井で、他には見られない仕様だった。後陣の入側、脇陣は化粧屋根裏だが、脇陣は地垂木とは異なる意匠としての垂木が架けられていた。
建具は、正面五間が蔀戸、両脇間は連子窓とし、側面前方二間は桟唐戸、次の二間は板壁、背面二間は板唐戸、内外陣境は吹き寄せの格子と菱格子欄間が入る。
組物は支輪付きの二手先で、滋賀県内の国宝中世本堂では常楽寺だけであるが、建立当初は出組だった。隅の組み物の肘木に禅宗様木鼻などの意匠も見られた。
所見
側柱上の組物には二手先が用いられ、華やかな意匠が施されている。また、組物を利用して外陣全面に天井を張り巡らせ、外陣の作りこみが見られた。一方で、内陣や後陣は簡素な作りとなっており、来訪者が目にする空間への徹底した演出と、視線の届かない場所との明確な対比が意図されているように感じられた。後世に組物を二手先に変更したことによって、高さの違いの解き方が少し複雑に見え、他の中世本堂との違いが明確に見えたのも興味深かった。
参考文献(新規ウィンドウが開きます)
文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/185606 (2025.7.24閲覧)
伊藤延男『国宝・中世日本の仏堂』(中央公論美術出版,2025)