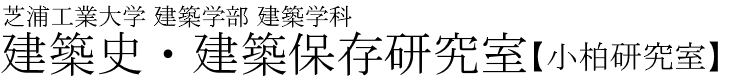見学 小柏研究室
2025/08/08
Visit Zensuiji Temple (Konan City, Shiga Prefecture, a national treasure)
文責:新村恵太(修士2年)
〇善水寺本堂
建立:室町前期
構造形式:桁行七間、梁間五間、一重、入母屋造、檜皮葺
正面二間を外陣、中央桁行五間、梁間二間を内陣、背面の側柱を後方にずらして広い一間の後陣とする。
外陣は入側柱に桁行方向三間分の虹梁を架けることによって、中央の入側柱2本を抜く。入側は化粧屋根裏で、内陣側は組入天井である。
内陣は須弥壇と独立柱を設けるが、独立柱は柱筋から背面にずらして立つ。内外陣の天井高さは一緒だが、内外陣境の柱を片蓋にし、内陣側を出組、外陣側を出三斗にすることで、内外陣境柱と内陣背面柱を繋ぐ虹梁の高さを確保する。
後陣は一間であるが、背面にずらした側柱と内陣背面柱を虹梁で繋ぎ、その上に束を立て、側桁を載せることで高さを調整する。桁行五間であるため、内陣背面柱が入側柱となり、後陣は化粧屋根裏となる。
建具は、正面中央間が桟唐戸、他は蔀戸、側面前方二間は蔀戸、次の一間と後方一間が桟唐戸である。内外陣境は格子戸と菱格子欄間が入る。
側柱上の組物は支輪付きの出組、内陣は出三斗で、場所による使い分けをしている。
所見
中世の密教仏堂の特徴として、外陣部分の柱を抜いて参拝空間を確保している点は共通した特徴であり、善水寺も同様に柱を抜いている。基本は入側柱から内外陣境柱の梁間方向に虹梁を架け、その上に組物や大瓶束を載せて柱を抜く。しかし、善水寺本堂は中央の入側柱の桁行方向三間分に虹梁を架けることで柱を抜いており、今まで見た中でこのような例は見たことがなかった。これにより、梁間方向にあるはずの虹梁をなくしつつ、天井高を上げて、限られた外陣の空間を広く見せる工夫だと考えた。また、内陣も柱筋をずらした位置に独立柱を立てることで内陣の法要空間を広くしている点や、後陣も背面にずらしている点などから、桁行五間の限られた規模の中でも構造に工夫を凝らした室町時代らしい仏堂であった。
見学時は屋根葺き替え中のため外観が見られなかったので、またの機会に訪れたいと思う。
参考文献(新規ウィンドウが開きます)
文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/194120 (2025.7.24閲覧)
伊藤延男『国宝・中世日本の仏堂』(中央公論美術出版,2025)